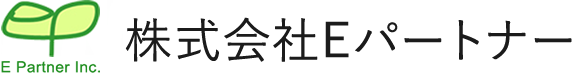職場のコミュニケーション改善はハラスメント防止に有効か
目次
職場で起こるハラスメントの実態
2024年5月に厚生労働省が公表した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間に勤務先で受けたハラスメントとして割合が高いのは、パワハラ(19.3%)、顧客からの著しい迷惑行為(10.8%)、セクハラ(6.3%)となっています。この並びは2020年度に実施された前回調査から変わっていません。
一方で、就職活動中またはインターンシップ参加中の学生が企業の従業員からセクハラを受けた割合は前回調査の25%から増加して30%を超えています。ハラスメントの対象は従業員だけでなく、就職を希望する学生にも広がっています。
仕事の意欲を減退させるカスタマーハラスメント
パワハラの次に発生の割合が高くなっているのが顧客からの著しい迷惑行為です。カスタマーハラスメントとしてメディアで取り上げられる機会も増え、自治体も対策に乗り出しています。具体的には顧客からの「継続的で執拗な言動」や「威圧的な言動」がカスタマーハラスメントとされます。長時間に及ぶクレームや暴言などは対応する従業員の怒りや不満、不安につながり、仕事への意識を減退させ、最終的には離職につながる可能性もあります。
カスタマーハラスメントの発生は企業も認識はしているものの、何らかの取り組みをしているケースは半数以下です。従業員への安全配慮の面からも、早めに何らかの取り組みを検討すべきかもしれません。
採用活動に影響する就活ハラスメント
近年、増加傾向にある就活ハラスメント。問題となる行動には従業員からの性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、不必要な身体への接触等があげられます。インターンシップ中の学生へのハラスメントには、性的な言動に対して拒否・抵抗したことによる不利益な取扱いといったことも含まれます。
就活ハラスメントが起こるタイミングは、企業のリクルーターと学生が会うとき、内々定を受けたときや受けた後が多くなっています。また、企業説明会やセミナー、採用面接といった場面でもハラスメントは起きています。ハラスメントを受けた学生は、就職活動に対する意欲減退のほか、眠れない、不安感、通院や入院といった状況にも追い込まれます。従業員がその立場を利用して起こす言動が採用活動を妨げ、学生の人生を変えてしまうことにもなりかねません。
これからの就職活動においては、ハラスメント対策がしっかりなされていない企業は敬遠され、優秀な人財の採用は難しくなるでしょう。ハラスメント対策は従業員だけでなく就職を希望する学生まで対象を広げて検討していく必要があります。企業のハラスメント対策は、従業員の働きやすさ向上だけでなく採用活動にもかかわる課題です。
効果的なハラスメント対策とは
ハラスメント防止対策として多くの企業で実施されている取り組みは「相談窓口の設置と周知」です。社内に加えて社外にも窓口を設置しているケースもあります。ハラスメントが起こる状況は多様であるため、相談窓口では相談者や行為者から丁寧に事実確認を行うことが必要とされています。窓口が複数設置されていれば相談を受ける担当者の業務負荷軽減にもなります。利用する窓口が選択できるのは利用者にとってもメリットとなるでしょう。
ハラスメントを防止する対策を検討する際に、よく取り上げられるのが職場内のコミュニケーションの改善です。厚生労働省の指針でも、ハラスメントの行為者・被害者になることを防止する上で労働者個人のコミュニケーション力の向上が重要であるとされています。なぜコミュニケーションの改善がハラスメントの防止になるのでしょうか。
コミュニケーションの改善はハラスメント防止に有効か
そもそもハラスメントとは何なのか、パワハラを例に確認します。
|
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。 あかるい職場応援団「ハラスメントの定義」 |
ハラスメントを引き起こすのは言動とされています。
では、コミュニケーションとはどのようなものでしょうか。いくつか辞書を引いてみると
| コミュニケーションとは、人の間で行われる感情・思考の伝達、意思の疎通である |
と定義できそうです。
感情・思考の伝達であるコミュニケーションを改善するには、その手段となる言葉や行動(言動)を振り返り、より良くしていくことになります。コミュニケーションの改善によって言葉や行動を適切に発信することができれば、人の言動が引き起こすハラスメントの防止にも効果が期待できると考えられます。
コミュニケーションの改善に必要なこと
実際にコミュニケーションが行われる場面では、その人が抱えている状況や感情によって言動が左右されることもあるでしょう。コミュニケーションの改善をハラスメントの防止につなげるには、感情をコントロールするスキルを身につけることも必要です。
組織内のコミュニケーションが改善されるまでには一定の時間を要するため、ハラスメントの防止対策としては遠回りに思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば有効な対策です。「相談窓口の設置」といった短期間で実現しやすい対策と組み合わせて実施すると、さらに効果的でしょう。
【まとめ】12月をハラスメント対策 再点検の機会に
厚生労働省では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりを進めるため、この時期に集中的な広報・啓発活動を実施しています。「職場のハラスメントに関する実態調査」では、ハラスメント対策を進めたことによる副次的効果として「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」「会社への信頼感が高まる」といった点が挙げられています。この機会に、社内のハラスメント対策を再点検してみてはいかがでしょうか。
(参考)
・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584512.pdf
・あかるい職場応援団 データで見るハラスメント「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」https://www.noharassment.mhlw.go.jp/foundation/statistics/
メンタルヘルスケアは「Eパートナー」のEAPサービスにお任せください!
社員のメンタルヘルスケアはEパートナーにご依頼ください。公認心理師や産業カウンセラー、臨床心理士の資格を保有する専門家集団が在籍し、カウンセリングやメンタルヘルス研修、メンタルケアのコンサルティングなど、トータルで企業様のEAPを支援。特にカウンセリングに関しては全国各地で対応可能です。社員の方のお悩みにしっかりと耳を傾け、いち早くストレス状況を把握し、先回りして対策をご提案します。
社員のメンタルヘルスが健全な状態になれば、職場の生産性も向上するはずです。Eパートナーならフットワークが軽く、タイムリーな対応も可能です。メンタルヘルスケアの課題はぜひご相談ください。