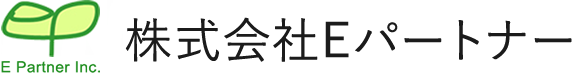やりがいが育つ組織づくりに必要なこと
目次
やりがいが芽生えるとき
働く人が仕事のやりがいを感じるのはどのような時でしょう。 目標を達成した時や感謝の言葉をもらえた時、成長を感じられた時などでしょうか。仕事のやりがいは、その仕事をする意義・目的と関連があります。仕事の意義・目的が明確であれば、やりがいを支える土台もしっかりとしたものとなります。 仕事の意義や目的を考えるときに引用される寓話があります。「3人のレンガ職人」の話です。エンゲージメントやキャリアをテーマにした研修でよく取り上げられるので、ご存じの方も多いかもしれません。お話に登場する人物のセリフなどは話し手により多少の違いがありますが、おおまかなストーリーは次の通りです。
3人のレンガ職人の話
ある旅人が旅の途中でレンガを積んでいる3人の職人に出会いました。ここで何をしているのかと尋ねると、 1人目の職人は「見ればわかるだろう。レンガを積んでいるのさ。」と答えました。 2人目の職人は「家族を養うためにレンガ積みの仕事をしているんだ。」と答えました。 3人目の職人は「大聖堂をつくっています。とても素晴らしい仕事をしているのです。」と答えました。 旅人は3人目の職人にお礼の言葉を残して、また元気に歩き出しました。
仕事をする目的は三者三様
同じ仕事(レンガ積み)でも、その目的はさまざまです。1人目の職人は単純な作業として、2人目は生活のため、3人目はさまざまな思いを持った人々が訪れる場所をつくるためにレンガを積んでいます。それぞれの目的についてもう少しイメージを広げてみましょう。
1人目の職人が仕事をする目的は、その日にやるべき作業をしっかり完了させることかもしれません。 2人目の職人の目的は家族を養うことです。仕事から得る報酬で家族の生活を支えることに意義を感じているのでしょう。 3人目の職人は人々が集まる大聖堂をつくることが目的です。自分の仕事に誇りを持っている様子も伝わってきます。完成した大聖堂に集まる人からの感謝の言葉が次の仕事へのモチベーションになりそうです。
目的を持つと仕事のやりがいは向上します。ただレンガ職人の目的が三者三様であるように目的となるものはひとつではありません。働く人それぞれに違った目的があります。
目的を見失うときもある
働く人が仕事をする目的を見失ってしまうのはどのようなときでしょう。 環境やライフステージに変化が起きた時がそのひとつです。変化によって、ものごとの捉え方や考え方がこれまでとは違ったものになることがあります。すると、仕事をする目的もこれまで通りではしっくりいかなくなってしまうのです。 仕事の生産性が落ちている人には何か変化が起きているのかもしれません。環境の変化はやりがいが萎んでしまうタイミングでもあります。そのような状態に周囲が気付き、その人の新たな価値観と仕事をつなげ直すサポートができれば、やりがいを萎めてしまうこともないでしょう。
やりがいを育むには
仕事をする目的が定まりやりがいが芽生えてきたら、その芽がしっかり根付くよう育てていく段階です。 ここで重要となるのが働く人と組織が共有する目標です。目標設定は毎年決まった時期に行って人事評価などに活用している企業も多いでしょう。目標設定時の適切なアドバイス・支援は働く人のやりがいを根付かせる要素のひとつです。せっかく芽生えたやりがいの芽をこの段階で摘んでしまわないように心得ておきたいポイントがあります。「他者の視点」と「小さなゴール」です。
他者の視点
一人で考えていると自分の常識の枠から抜け出すことが難しくなります。個人の目標だとしても、そこに他者の視点を取り入れることで自分の枠を超えた目標設定が可能になります。 これまでとは異なる視点で設定した目標から思いもよらない成果が引き出されるかもしれません。目標設定だけでなく、普段から相談がしやすい組織風土は働く人の可能性を広げ、やりがいも育てます。
小さなゴール
大きな目標には達成までのステップとして小さなゴールをいくつか用意しておく方法がおすすめです。 少しずつでも前に進んでいる感覚があると停滞感や行き詰まり感が招く不安やイライラを感じにくくなります。また、無益なことに囚われず目の前の行動に集中して進んで行けるというメリットもあります。たとえ小さなことでも「できた」という感覚を大切にして積み重ねていくと、やがて「できる」という自信になります。自信はやりがいを育てるひとつの要素です。
働く人と充分なコミュニケーションをとり、互いに納得感のあるテーマを目標に落とし込みましょう。
やりがいを根付かせるために
働く目的を見つけ自分らしい働き方を実現できたとしても、仕事を続けていればストレスを感じたり、やりがいを見失ったりする場面に遭遇することもあるでしょう。そんな場面で役立ててほしいのが「ジョブ・クラフティング」の考え方です。 「ジョブ・クラフティング」とは働き方を工夫して仕事のやりがいや満足度を高める手法です。個人向けではありますが、他者の支援やサポートをするときにも参考になります。
状況を改善する3つの観点
「ジョブ・クラフティング」には3つの観点があります。
◇作業クラフティング
仕事のやり方への工夫。スケジュール管理や仕事量の調整など。
◇人間関係クラフティング
周囲の人への働きかけの工夫。自分から積極的にアドバイスを求めにいくなど。
◇認知クラフティング
仕事の捉え方への工夫。従事している仕事の目的や意義を考えてみるなど。
例として「仕事に不満がある」という相談を受けたケースを考えてみましょう。この相談対応に「ジョブ・クラフティング」を活用すると次のようになります。
1)まずは、本人が感じている不満の源は何なのかを探っていきましょう。
2)次に、3つの観点「仕事のやり方」「周囲の人との関係」「仕事の捉え方」のうち、どこにどのような工夫を加えれば本人の不満が解消するのかを考えます。
3)浮かんだアイデアから実際にできそうなことを試します。ここで状況が改善すれば良いですし、改善しなければ別の方法を試します。
このサイクルを回しながら課題の解決を目指していきます。不満を抱えている本人と話し合いながら進めていくといいですね。上手くいかないこともある
「ジョブ・クラフティング」は働く人と仕事との良い関係をつくります。仕事への向き合い方が前向きになればストレスは低減、やりがいも育ち根付いていきます。 そうはいっても実際には上手くいかないこともあるでしょう。辛さや苦しさを抱えている人には、その人の話にじっくり耳を傾けることもひとつの支援です。ただし本人の状況によっては産業保健スタッフや専門家につなげるといった対応も必要です。支援やサポートをする立場であっても、ひとりで抱え込まないようにしましょう。
【まとめ】組織づくりに、働く人のやりがいを育むという視点を
この記事では、働く人のやりがいを育てる方法をご紹介しました。仕事のやりがいはその仕事をする目的を定めることで芽吹き、適切な目標設定で育ち、満足度を高める工夫で根付いていきます。働く人がやりがいをもって仕事に取り組んでいくには組織としての体制づくりも欠かせません。人材の流出を防ぎ高い生産性を生む組織づくりに、働く人のやりがいを育てるという視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。
(参考)
厚生労働省「令和元年版労働経済の分析」-人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06963.html
メンタルヘルスケアは「Eパートナー」のEAPサービスにお任せください!
社員のメンタルヘルスケアはEパートナーにご依頼ください。公認心理師や産業カウンセラー、臨床心理士の資格を保有する専門家集団が在籍し、カウンセリングやメンタルヘルス研修、メンタルケアのコンサルティングなど、トータルで企業様のEAPを支援。特にカウンセリングに関しては全国各地で対応可能です。それぞれのお悩みにしっかりと耳を傾け、解決へ向けて支援します。
社員のメンタルヘルスが健全な状態になれば、職場の生産性も向上することでしょう。Eパートナーならフットワークが軽く、タイムリーな対応も可能です。メンタルヘルスケアの課題はぜひご相談ください。